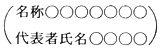○清水町公用文作成に関する規程
平成6年3月29日訓令第4号
清水町公用文作成に関する規程
清水町公用文作成に関する規程(昭和41年清水町訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1 総則
第2 文体
第3 用字
第4 用語
第5 仮名遣い
第6 送り仮名の付け方
第7 書き方
1 文章の書き始め
2 地名の書き表し方
3 外来語の書き表し方
4 人名の書き表し方
5 振り仮名の付け方
6 数字の書き表し方
7 ローマ字のつづり方
第8 符号
1 区切り符号の用い方
2 繰返し符号の使い方
3 「・」(ピリオド)
4 「:」(コロン)
5 「~」(なみがた)
6 傍点及び傍線
7 見出し記号
第9 文書の書式
1 許可、認可、指令の場合
2 一般文書の場合
3 主な書式例
4 文書のとじ方
5 用紙
第10 条例・規則の書式
1 公布文
2 番号
3 題名
4 目次
5 本則
6 附則
7 書式
第11 訓令の書式
1 制定(全文改正)
2 一部改正
3 廃止
第12 告示その他公告の書式
1 告示
2 公告
参考 条例・規則の改正の書式例
第1 総則
公用文の用語、用字、文体等については、「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)によることを原則とするが、特に注意を要する事項は、第2以下において定める。
第2 文体
1 公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、公告及び告示の類並びに往復文書(通知・回覧・願・届・申請・照会・回答・報告等を含む。)の類は、なるべく「ます」体を用いる。
〔注〕(1) 「だ、だろう、だった」の形は、「である、であろう、であった」の形にする。
(2) 打消の「ぬ」は、「ない」の形にする。「ん」は、「ません」のほかは用いない。「せねば」は、「しなければ」とする。
2 文語体の表現は、なるべくやめて、平明なものとする。
〔注〕(1) 口語化の例
これが処理→その処理 せられんことを→されるよう
ごとく・ごとき→のような・のように
進まんとする→進もうとする
貴管下にして→貴管下で(あって)
(2) 「主なる・必要なる・平等なる」などの「なる」は「な」とする。
(3) 「べき」は、「用いるべき手段」「考えるべき問題」「論ずべきではない」「注目すべき現象」のような場合には用いてもよい。「べく」、「べし」の形は、どんな場合にも用いない。
(4) 漢語につづく「せられる、せさせる、せぬ」の形は、「される、させる、しない」とする。「せない、せなければ」を用いないで、「しない、しなければ」の形を用いる。
(5) 簡単な注記や表などの中では、「あり、なし、同じ」などを用いてもよい。
〔例〕「配偶者…あり」「ムシバ…上1、下なし」「現住所…本籍地に同じ」
3 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞や接続助詞などを用いて文章を長くすることを避ける。
4 文の飾、あいまいな言葉、まわりくどい表現は、できるだけやめて、簡潔な論理的な文章とする。
敬語についても、なるべく簡潔な表現とする。
〔注〕(1) 時及び場所の起点を示すには、「から」を用いて、「より」は用いない。
「より」は、比較を示す場合にだけ用いる。
〔例〕東京から京都まで。
午後1時から始める。
恐怖から解放される。
町長から説明があった。
(2) 推量を表すには「であろう」「だろう」を用い、「う、よう」を用いない。「う、よう」は、意思を表す場合にだけ用いる。
〔例〕 | 役に立つであろう(だろう) | 
|
そのように思われるであろうか(だろうか) |
対等の関係に立とうとする | 
|
思われようとして |
(3) 並列の「と」は、まぎらわしいときには最後の語句にも付ける。
〔例〕横浜市と東京都の南部との間
(4) 「ならば」の「ば」は略さない。
5 文書には、できるだけ、一見して内容の趣旨が分かるように、簡潔な標題を付ける。また、「通知」「回答」のような、文書の性質を表す言葉を付ける。
〔注〕〔例〕予算要求に関する件→予算要求について(通知)
6 内容に応じ、なるべく箇条書きの方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とする。
第3 用字
1 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲内で用い、字体については通用字体を用いるものとする。なお、地名・人名等の固有名詞などは、常用漢字以外であっても、しいて仮名書きにする必要はない。ただし、読みにくいと思われるような場合は、必要に応じ、振り仮名を用いる等、適切な配慮をする。
2 仮名は、平仮名を用い、片仮名は次のような場合に用いる。ただし、外来語でも「かるた」、「たばこ」などのように、外来語の意識の薄くなっているものは、平仮名で書いてよい。
外国の地名・人名および外来語
イタリア フランス ロンドン
エジソン ヴィクトリア
ガス ガラス ソーダ ビール ボート マッチ等
3 常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては、次の事項に留意する。
(1) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。
例 彼 何 僕 私 我々
(2) 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。
例 必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り 至って 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明るく 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)
ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。
例 かなり ふと やはり よほど
(3) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。
例 御案内 御調査
ごあいさつ ごべんたつ
(4) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。
例 げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)
(5) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。
例 おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに
ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。
及び 並びに 又は 若しくは
(6) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。
例 ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。)
ぐらい(二十歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。)
ほど(三日ほど経過した。)
(7) 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として仮名で書く。
例 こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。)
ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。)
とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか)
ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(その点に問題がある。)
いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。)
できる(だれでも利用ができる。)
…てあげる(図書を貸してあげる。) …ていく(負担が増えていく。)
…ていただく(報告していただく。) …ておく(通知しておく。)
…てください(問題点を話してください。) ない(欠点がない。)
…てくる(寒くなってくる。) …てしまう(書いてしまう。)
…てみる(見てみる。) …かもしれない(間違いかもしれない。)
…にすぎない(調査だけにすぎない。) …について(これについて考慮する。)
なお、常用漢字表の本表に掲げていない漢字・音訓を用いて書き表す語は、次に示すとおり従来どおり仮名で書く。
ア 代名詞
例 これ それ どれ ここ そこ どこ だれ いずれ
イ 副詞及び連体詞
例 こう そう どう いかに ここに とても なお ひたすら やがて
わざと わざわざ じらい ひっきょう
この その どの あらゆる いかなる いわゆる ある(~日)
ウ 接頭語
例 お願い み心 かき消す
エ 接尾語
例 子供ら 5分ごとに 若者たち お礼かたがた
オ 接続詞
例 しかし しかしながら そうして そこで そして
カ 助動詞及び助詞
例 次のように考えた。 15日までに提出すること。 歩きながら話す。
資料などを用意する。
キ 次のような語句
例 そのうちに連絡する。 雨が降ったため中止となった。
10時に到達するはずだ。 原本のままとする。 東京において開催する。
書いてやる。 前例によって処理する。 1週間にわたって開催する。
4 常用漢字表で書き表せないものは、次の標準によって書き換え・言い換えをする。
(1) 漢字をはずしても意味のとおる使い慣れた言葉は、そのまま仮名書きにする。
さかのぼる(遡) ゆだねる(委ねる) あっせん(斡旋) でんぷん(澱粉)
(2) ほかに良い言い換えがなく、又は言い換えをしては不都合なものは、常用漢字表にはずれた部分を仮名書きにする。
右げん(右舷) 口こう(口腔)
(3) 同じ音の意味の似た漢字に書き換える。
車両(輌) 編集(輯) 保育(哺) 放棄(抛) 用人(傭)
(4) 意味の似ている使い慣れた言葉に書き換える。
雑報(彙報) 改心(改悛) 開封(開披) 押印(捺印) 申請(禀請)
(5) 同じ意味の新しい言葉を工夫して使う。
損傷(毀損) 汚職(涜職) 戒告(譴責) 災害救助金(罹災救助金)
(6) 易しい言葉で言い換える。
消す(抹消する) 触れる(牴触する) 破る(破毀する) 酔う(酩酊する)漏らす(漏洩する)
5 常用漢字表で書けるものでも次の複合語のような場合は、なるべくその全部又は一部を仮名書きする。
(1) 意味がその語の本来の意味からあまり離れているとき。
ありがたい(有難) あいそう(愛想)
…していただく(…して頂く)
ただし、術語などで漢字で書く慣用のあるものはこの限りでない。
差入れ 差押え 取調べ 打合せ
(2) 一語としての意識が強いとき。
あおむく(仰向) くどく(口説)
(3) 漢字で書くと誤解されるおそれがあるとき。
大ぜい(勢) 出どころ(所)
第4 用語
1 特殊な言葉や、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。(×印は、常用漢字表にない漢字であることを示す。)
救う(救援する) 処置(措置) かなった(即応した) 一つとして(一環として) 適当な処置をとる(善処する)
2 言いにくい言葉を使わず、口調の良い言葉を用いる。
受け入れない(拒否する) 妨げる(はばむ)
3 音読する言葉はなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。
川(河川) 橋(橋梁) ほこり(塵埃) まぶた(眼瞼) 述べる(陳述する) 埋める、詰める(充填する) かたく守る(堅持する)
4 音読する言葉で意味の二様にとれるものは、なるべく避けて、ほかの同じ意味の言葉を用いる。
歩調を合わせる(協調する) …「強調する」とまぎれやすい。
勧める(勧奨する) …「干渉する」とまぎれやすい。
心から(喪心から) …「中心から」とまぎれやすい。
5 漢語をむやみに続けると意味がとりにくくなるから、接続詞を適当に用いるように工夫する。
強制疎開地の賃貸契約解除(公告) …(強制疎開地跡地賃貸契約解除公告)
最寄りの保健所を経由して提出しなければならない
…(最寄保健所経由提出しなければならない)
6 その他次によるものとする。
(1) 同音語について
ア 次のものは、一般に用いられるものだけを残し、一般的でないものは、今後他の表現を考える。

| 遺棄 | 
| 看守 |
委棄(用いない。) | 監守(用いない。) |

| 不正 | 
| 会議 |
不整(用いない。) | 開議(用いない。例えば、「会議を開く」とする。 |
イ 双方ともよく用いられて、紛れやすい次のものは、そのうちの一方又は双方を一定の形に言い換えて用いる。

| 解任 | 
| 看護 |
改任→改めて任ずる、交代 | 監護→監督保護 |

| 看守 | 
| 起因 |
管守→保管 | 基因→基づく |
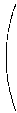
| 商標 | 
| 正規 |
証票→証明書、証片、証紙 | 成規→所定 |
証標→徴票、印 | 
| 調整 |
証憑→証拠 | 調製→作成 |

| 表決 | 
| 報償 |
評決→議決 | 報奨→奨励 |
ウ 次のものは統一して用いる。
改定 | 
| 改定 | 規律 | 
| 規律 | 定年 | 
| 定年 |
改訂 | 紀律 | 停年 |
干渉 | 
| 干渉 | 作成 | 
| 作成 | 統括 | 
| 統括 |
関渉 | 作製 | 統轄 |
関与 | 
| 関与 | 主管者 | 
| 主管者 | 配布 | 
| 配布 |
干与 | 主幹者 | 配付 |
規制 | 
| | 状況 | 
| 状況 | 表示 | 
| 表示 |
規正 | 規制 | 情況 | 標示 |
規整 | | 提出 | 
| 提出 | 総括 | 
| 総括 |
招集 | 
| 招集 | 呈出 | 総轄 |
召集 | | | | | | |
エ 同音語でも、意味の紛れるおそれのない次のようなものは、そのまま用いる。
(2) 似た意味の言葉
次の言葉は統一して用いる。
交代 | 
| | 証拠 | 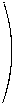
| | 趣意 | 
| | |
更代 | 交代 | 証徴 | 証拠 | 旨趣 | 趣旨 |
交迭 | | 憑拠 | 趣旨 | |
左の | 
| 次の | 証憑 | | 正当な理由 | 
| 正当な理由 |
次の | | | | 正当な事由 |
(3) 意味の通じにくい、難しい言葉
ア 次の言葉は、表現が簡単すぎて分かりにくいので、一般に通じやすい表現に改める。
監護→監督保護 蚕蛹→蚕のさなぎ 臨検→立入検査
イ 次の言葉は、似た意味の漢字を重ね合わせて、強いて難しく作られているので、それぞれ分かりやすい日常語に改める。
遺脱→忘れる 開披→開く 戸扉→戸
送致→送る、送付 申述→述べる、申立て
塵芥→ごみ 堆積→積もる 編綴→とじる、とじ合わせる
湧出→わき出る 歪曲→ゆがめる 漏泄、漏洩→漏らす
ウ 次の言葉は、分りやすい外来語に改める。
堰堤→ダム 空気槽→空気タンク 鬚髯→ひげ
油槽→油タンク
エ 次のような漢語の使用は、できるだけ避けて、それぞれ他の分りやすい表現に改める。
永期→長期 行用→行使 賜与(用いない)
(4) 常用漢字表にはずれた漢字を用いた言葉
ア 仮名書きにしても誤解の起こらない次の言葉は、仮名で書く。この場合、仮名の部分に傍点を付けることはやめる。
強姦→ごうかん 芥溜→ごみため 昏酔→こんすい
屠殺→とさつ 賭博→とばく 煉瓦→れんが
猥褻→わいせつ 罠→わな 賄賂→わいろ
煙草→たばこ 以て→もって 外廓→外郭
此→この 之→これ 其→その
為→ため 等(ら)→ら
(ア) 仮名書きにする場合、単語の一部分だけを仮名に改める方法はできるだけ避ける。
あっ旋→あっせん と殺→とさつ
(イ) 漢字を用いた方が分かりよい場合は、この限りでない。
あて名 ちんでん池 ほうろう鉄器
イ 次のものは、常用漢字表に外れた部分を、それぞれ一定の他の漢字に改めて書く。
慰藉料→慰謝料 外廓→外郭 繋留→係留
交叉点→交差点 雇傭→雇用 撒水管→散水管
侵蝕→侵食 訊問→尋問 洗滌→洗浄
碇泊→停泊 緬羊→綿羊 剰す→余す
ウ 次のものは、それぞれ他の一定の言葉に言い換える。
淫行→みだらな性行為 捺印→押印 瑕疵→きず、欠陥
毀損→損傷 橋梁→橋 竣功→完成
蔬菜→野菜 貼付→はり付ける 牴触→触れる、抵触
顛末→始末、事の経過 播種→種まき 封緘→封
瘋癲者→精神病者 烙印→焼印 狼狽→ろうばい、慌てる
エ 常用漢字表にない漢字を用いた専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で書くと理解することができないと認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。
砒素 蛾 禁錮
(5) 常用漢字表にあっても、仮名で書くもの
虞、恐れ→おそれ 且つ→かつ 従って(接続詞)→したがって
但し→ただし 但書→ただし書 外→ほか
又→また 因る→よる
第5 仮名遣い
仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。
第6 送り仮名の付け方
送り仮名の付け方は、原則として、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」・「例外」、通則7及び「付表の語」(1のなお書きを除く。)によるものとし、複合の語(通則7を適用する語を除く。)のうち、活用のない語であって読み間違えるおそれのない語については、次のように送り仮名を省くこととする。
明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 受入れ
受皿 受持ち 受渡し 打合せ 打合せ会 打切り
埋立て 売出し 売主 売値 売場 売渡し
帯留 折詰 卸値 買上げ 買入れ 買受け
買手 買値 買物 書換え 貸金 貸越し
貸室 貸出し 貸付け 貸主 借換え 刈取り
缶切 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 組合せ
組入れ 組替え 組立て 繰上げ 繰入れ 繰越し
繰延べ 差押え 差引き 下請 締切り 備付け
染物 田植 立替え 月掛 付添い 月払
月割 積立て 積荷 手続 届出 取扱い
取替え 取決め 取消し 取下げ 取締り 取調べ
取立て 取付け 投売り 抜取り 飲物 乗換え
乗組み 話合い 払下げ 払渡し 控室 引受け
引換え 引込み 日雇 日割 前払 見合せ
見積り 見習 申合せ 申込れ 申込み 申出
持込み 焼付け 雇入れ 雇主 呼出し 割当て
割増し
第7 書き方
1 文章の書き始め
(1) 文章の書き始め及び行を改めたときは、初めの1字分を空白にする。
(2) 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるものは、行を改めない。「なお」又は「おって」で始まるものは、行を改める。
2 地名の書き表し方
(1) 地名は、差し支えのない限り、仮名書きにしてもよい。
地名を仮名書きにするときは、現地の呼び名を基準とする。ただし、地方的ななまりは、改める。
(2) 地名を仮名書きにするときは、現代仮名遣いを基準とする(振り仮名の場合も含む。)。
(3) 差し支えのない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。また、常用漢字表以外の漢字についても、常用漢字表の通用字体に準じた字体を用いてもよい。
3 外来語の書き表し方
外来語の書き表し方については、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によるものとし、一般的に用いる仮名で書く。
4 人名の書き表し方
(1) 人名は、差し支えのない限り、常用漢字表の通用字体を用いてもよい。
(2) 事務用書類には、差し支えのない限り、人名を仮名書きにしてもよい。
(3) 人名を仮名書きにするときは、現代仮名遣いを基準とする。
5 振り仮名の付け方
漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける。
6 数字の書き表し方
(1) 数字は、アラビア数字を用い、漢数字は用いない。ただし、次のような場合には漢数字を用いる。数の感じを失した熟語・固有名詞などの場合は次の例による。
固有名詞 四国、九州、二重橋
概数を示す語 二・三日、四・五人、数十日
数量的な感じの薄い語 一般、一部分、四分五裂
単位として用いる語 120万、1,200億
慣習的な語 一休み、二言目、二日間続き、三月(みつきと読む場合)
(2) 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号等は、区切りを付けない。
(3) 少数、分数及び帯分数は次の例による。
少数…0.123
分数…

又は2分の1
帯分数…

(4) 日時、時刻及び時間は次の例による。ただし、日付は、原則として元号を用いることとし、必要に応じ西暦に置換え又は併記できるものとする。
普通の場合 | 日付 平成6年4月1日 |
時刻 10時10分 |
時間 9時間20分 |
省略する場合 | 平成 6. 4. 1 |
(5) 数字で年月又は期間を表す場合において、期間の月と暦の月と混同される場合は、「か」又は「箇」(漢数字に続く場合など)を用いる。
7 ローマ字のつづり方
ローマ字は、ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)によるものとする。
第8 符号
1 区切り符号の用い方
(1) 区切り符号は、主として文章の構造、語句の関係を明らかにするために用いるものであり、その種類は、おおむね次のとおりである。
。(まる) 、(てん) ・(なかてん) ( )(かっこ) 「 」(かぎ)
(2) 「。」(まる)
ア 「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。
「かっこ」の中でも、文の言い切りには、必ず用いる。
イ 「…すること」「もの」「者」「とき」「場合」などで列記される各号の終りにも、「。」を用いる。ただし、事物の名称を列記する場合には、「。」を用いない。
(ア) 「。」を用いる例
例…次の国事に関する行為を行う。
(1) 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(2) 国会を召集すること。
(イ) 「。」を用いない例
例…次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 主な漁業根拠地
(3) 船名
ウ 次のような場合には、「。」を用いない。
(ア) 題目・標語その他簡単な語句を掲げる場合
(イ) 言い切ったものを、かっこを用いずに「と」で受ける場合
例 政府の見解は、主権の所在の問題と国体との問題とは、別個の問題であるとの立場にあることを明らかにしている。
(ウ) 疑問・質問の内容をあげる場合
例 いかなるローマ字の形式を採用するかを決定する。
次の会合は、いつ開かれるか、折り返し御返事願いたい。(「。」の代りに「、」を用いた例)
(3) 「、」(てん)
ア 「、」は、一つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて、かえって全体の関係が不明になることのないようにする。
例 第4条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。
イ 「、」を用いるのは、次のような場合である。
(ア) 叙述の主題を示す「は」、「も」などの後
例 委員長は、会務を総理する。
この条例は、公布の日から施行する。
私は、何年何科試験に合格したものですが、次の科目は、何科試験で受験した科目ですから、その試験を免除されるようお願いします。
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
(注) 主語述語の関係にある簡単な語句が、条件の句の中又は文の末にあるときなどには、叙述の主題を示す「は」「も」などの後でも「、」を用いないでもよい。
(イ) 対等に並列する同種類の語句の間
a 一つの文の中に、叙述の語句その他用言を中心とする語句を並列するとき。
例 電報中継順路を次のように定め、昭和21年6月21日から施行した。
許可を受けた船舶が滅失し、沈没し、又は国籍を失ったとき。
船舶を譲り受け、若しくは借り受け、又は貸し付けた船舶の返還を受けて、かつお、まぐろ漁業の許可を受けようとするときも…
(注) 並列する語句が簡単なときは、「、」を用いないことがある。
例 地積を増し又は減じて権利の目的たる土地又はその部分を指定する場合…
b 体言又は体言を中心とする語句を並列するとき。
例 委員及び臨時委員は、政治、教育、宗教、文化、経済、産業等の各界における学識経験ある者の中から文部大臣がこれを任命する。
(注) 接続詞「及び」「又は」など又は助詞「と」「や」「か」などを用いて事物の簡単な名称を並列するときは、「、」を用いない。
例 かつお、まぐろ、かじき又はさめを、釣り又は浮きはえなわで捕る漁業…
相続人、合併後存続する法人若しくは合併によって設立した法人又は精算人…
神社、寺院及び仏堂並びに国有又は公有の墳墓地を管理する寺院及び仏堂は…
(注) 体言を並列する場合には、「、」の代りに「・」(なかてん)を用いることができ、また「、」と「・」とを併せ用いることができる。
例 工業学校では、工場要領・専門学科目の教授、実験・実習の施設並びに特別講義等の中で、労働管理・安全衛生その他一般の福利施設に関する知識を適当に要請させるようにしたい。
c その他の語句を並列するとき。
例 政治的、経済的又は社会的関係において…
ただし、事前に、事宜によっては事後に、国会の同意を経ることを…
(ウ) 文の初めに置く接続詞及び副詞の後
例 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、…これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって…
衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院解散の場合には、…
(注1) 文の初めに用いる接続詞及び副詞には、次のような語がある。
また なお ただし もっとも
そうして そして その上 しかも
それゆえ それで そこで したがって それならば それでは
ところで ついては
しかし しかしながら けれども ところが そもそも さて
すなわち なかんずく
もし たとえ たとえば
(注2) 語句を並列する接続詞は
(1) 簡単な事物の名称を並列するときは、その接続詞の前後ともに「、」を用いない。
((イ)b項の「注意」参照)
(2) その他の語句を並列するときには、その接続詞の前に「、」を用いる。
((イ)a項参照)
(エ) 叙述に対して限定を加え条件をあげる語句の後
a 主題として提示する語の前に、叙述に対する限定・条件の語句を冠するとき。
例 このたび自治省設置法が施行されたので、従前の達、通達、告知等に掲げた官署名、官職名等は、別に規定する場合を除くほか、それぞれ変更されたものとする。
b その他限定・条件の語句を用いるとき。
例 専門委員は、委員長の要求に基づいて、関係各課の職員及び学識経験のある者のうちから、各課長の推せんによって、市町村長が任命する。
次の期限までに完納されないときは、やむを得ず、地方税法の規定によって、財産差押をしなければならないことになりますから、特に御注意願います。
(注) 次のような場合には「、」を用いない。
(1) 限定・条件の語句が、簡単で比較的直接に後の語句に続く場合
例 かつお・まぐろ漁業の許可は、次の場合にその効力を失う。
内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。
(2) 限定・条件の語句が、ひとまとまりと考えられる大きな限定・条件の語句の中に含まれている場合
例 都道府県知事は、市町村長から人口動態統計月報の送付を受けたときは、これを検査して記入もれ、計算誤り等があればこれを当該市町村長にたずねて訂正した上、報告した市町村名を記入した送り状を添えて、調査月の翌月20日までに内閣統計局に送付しなければならない。
(注) 限定・条件の語句をつくる助詞及びこれに準ずるものには、次のような語がある。
が を から で
には(するには) ため〔に〕 よう〔に〕
として〔は〕 について〔は〕 において〔は〕 を除いて〔は〕
を基本として に立脚して に応じて に先立って
に関し〔ては〕 に対し〔ては〕 により(によって)
のもとに とともに 上で
限り のほか 以外は のうち にかかわらず
ば(あれば なければ) とき〔は〕 場合に〔はも〕
のち 前に 以内に の際 の間
ゆえに ので から
ても とも のに けれども が
と ながら ずに ないで たり し
(注) 次のような場合には、ひとつづきのものとして、間に「、」を用いない。
がある(がない) ができる(はできない)
である(ではない)
をする を認める を公布する
とする という と思う と信ずる を必要とする
ていく てくる ておく てしまう てみる
なければならない てはならない
(オ) 体言に対して限定し修飾する語句には、原則として「、」を用いない。
例 日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意思により決定される。
日本国の国家意思の源泉が日本国民の全体に存することを宣言したものである。
(注) 次のような場合には「、」を用いることがある。
(1) 語句をへだてて限定、修飾するとき。
例 国際連合自身も理想として掲げているところの、戦争は国際平和団体に対する犯罪であるとの精神を、率先して実現する。
天皇の地位は、国と国民統合の表象という、精神というか、儀礼というか国民感情の表現として規定された。
(2) 並列した体言を等しく限定修飾するとき。
例 …優秀な成果を収め得た、著者の豊富な学力と洗練された説述とは、推賞に値するものと認められる。
(カ) 条項の順序を示す記号には、原則として「、」を用いず、その下に空白を置く。ただし、行を変えずに各号を列記するとき及び本文に続けて読まれるおそれのあるものがあるときは、統一して「、」を用いる。
ウ 「、」の用いようでは誤解を生ずる場合がある。
(ア) 次のような例では、「、」を用いると誤解を生じやすい。
例 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
(イ) 次のような例では、「、」を用いないと誤解を生じやすい。
例 刑事被告は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、…
(ウ) 次のような例では、「、」を用いないと読みにくい。
例 仮名、若しくは漢字
塩水で煮熱し、伸展機にかけて、伸ばしたもの
(4) 「・」なかてん
ア 「・」は、体言を並列するときに、「、」の代りに、又は「、」と併せて用いられる。
例 天皇陛下は、地方状況御視察のため、きたる6月4日御発、京都・大阪・和歌山・兵庫各府県へお出ましの上、同15日お帰りの御予定である。
イ 「・」は前記のほか、外来語、外国の地名・人名、ローマ字、日付等について次のように用いられる。
例 ダグラス・マッカーサー ニューヨーク・タイムズ紙 ジュニア・ハイ・スクール運動 フロッピー・ディスク Y・M・C・A
平成6・11・3
(注) 外国語・外国の地名・人名及び「・」を用いたものを並列するときには、もっぱら「、」を用いる。
例 リンカーン、ゴッホ、シューベルト
ナイチン・ゲール、ジャンヌ・ダルク
(5) ( )(かっこ)「 」(かぎ)
ア ( )は、一つの語句又は文の後に注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。
例 大蔵大臣は、特定商社の職員で日本人たるものの中から、管理人を選任して、特定商社の財産で本邦内にあるもの(以下「特定商社」という。)の管理にあたらしめる。
3月間に得た賃金の総額を、その労働日数(実働)で除した金額…
(注) ( )の中で更に必要のあるときは、〔 〕(そでがっこ)を用いる。
なお、〔 〕は、見出しに用いることがある。
イ 「 」は、引用する語句若しくは文、又は特に示す必要のある語句を挟んで用いる。
例 第9条第2項に「国の交戦権はこれを認めない。」とあるのは、この「自衛権の行使」による戦争までも、これを禁止したものである。
(注) 「 」の中で更にかっこを用いるときは『 』(ふたえかぎ)を用いる。引用の原文に「 」が用いてあるときは、原文の「 」を『 』に改める。
2 繰返し符号の使い方
繰返し符号には、次の符号が用いられるが、公用文には「々」以外は使わない。
々 ゝ ゞ「

」
「々」は、漢字1字の繰返しの場合に用いる。
例 人々 国々 年々 日々 何々 烈々 時々
ただし、次のような異なった意味で用いる場合には「々」を用いない。
例 民主主義 学生生活 委員会会則 事務所所在地
3 「・」(ピリオド)は、単価を示す場合、見出し記号に付ける場合及び省略符号とする場合に用いる。
例 1,234.00円 0.12
平成 7. 1. 1 N.H.K
4 「:」(コロン)は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
5 「~」(なみがた)は、「…から…まで」を示す場合に用いる。
例 第1号~第10号 東京~大阪
6 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。
例 かん詰 ぼう然
公文書をやさしく書くことは、能率的である。
7 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は、努めて使わないようにする。
第1 | | 1 | | (1) | | ア | | (ア) | | a | | (a) |
1 | | | | | | | | | | | | |
(1) | | | | | | | | | | | |
| ア | | | | | | | | | | |
| | (ア) | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | |
| | | | (a) | | | | | | | |
見出し記号は、句読点を打たず、1字空けて次の字を書き出す。
第9 文書の書式
1 許可、認可、指令の場合
(1) 文書番号は、左上方1字目から書き始める。
(2) あて名は、用紙の中央から書き出して、終りは1字空ける。あて名に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書き出し、終りは1字空ける。
(3) 本文は、1字空けて書き出す。
(4) 年月日は、左に1字空けて、だいたい終りが中央にくるようにする。
(5) 町長名は、左に寄せて書き出し、公印を押した後、1字空くようにする。
(6) 公印は、町長名の最後の文字の中央に掛かるよう押印する。
(7) 契約は、原議を下にし、許可書等の上端中央に押す。
2 一般文書の場合
(1) 文書番号は、用紙の中央やや左から書き出し、終りは2字空ける。
(2) 年月日は、文書番号の下の行に、文書番号と書出しをそろえて書く。
(3) あて名は、第2字目から書き出し、名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(4) 町長名は、用紙の中央やや右から書き出し、公印を押した後、1字空くようにする。
(5) 公印は、町長名の最後の文字の中央に掛かるよう押印する。
(6) 標題(件名)は、3字空けて書き出し、書ききれないときは、その行の終りを2字空けて行を改める。この場合、標題の末尾には、「通知」、「照会」、「回答」、「報告」等を括弧書きし、文書の種類を明らかにする。
(7) 「なお書き」及び「おって書」は、行を改める。この場合、両方を使うときは、「なお書き」を先にする。
また、「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは、中央に書く。
(8) 契印は、原議を下にし、発送文書の上端中央に押す。
3 主な書式例は、次のとおりとする。
(1) 許可、認可
○○許(認)第○○号 | |
○○○○○×○○○○× |
(職名等) (氏名) |
×○○○年○月○○日○○第○○号で申請のあった○○○○○○○については、○○○条例(○○○年清水町条例第○○号)第○条第○項の規定に基づき許可(認可)する。 |
×○○○年○月○○日 |
清水町長×○○○○ × × |
| (氏名) |
(注)(1) 法令、条例、規則等の規定に基づいて権限を行使するための文書は、法令、条例、規則等の根拠を示すものとする(以下各書式について同じ。)。
(2) ×印は、空白にする数字を示す(以下各書式について同じ。)。
(3) 左上端の「○○」には、清水町の頭文字を付けることを例とする(以下各書式について同じ。)。
(2) 訓・内訓
訓(内訓)第 号 |
令 達 先× |
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する(しなければならない)。 |
×× 年 月 日 |
清水町長×氏 名 × × |
(3) 達書式例
6(記号)第 号達 |
令 達 先× |
×何々法(○○○年法律第○○号)第○○条の規定により○○○○○○○○○命ずる(取り消す)。 |
×× 年 月 日 |
清水町長×氏 名 × × |
(4) ア 指令(例1)
6(記号)第 号指令 |
(…経由) |
令 達 先× |
×○○○年○○月○○日申請の○○○○○○○する。ただし、次の条件を守らなければならない。 |
×× 年 月 日 |
清水町長×氏 名 × × |
1×○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○。 |
イ(例2)
6(記号)第 号指令 |
令 達 先× |
×○○○年○○月○○日申請の○○○年度○○○○に対し、○○○○○により金○○○○円を補助する。ただし、次の事項を承知されたい。 |
××○○○年○○月○○日 |
清水町長×氏 名 × × |
1×○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○。 |
(5) 承認
○第○○○号× |
○年○月○日× |
×○○○○×○○○○様 |
清水町長×氏 名 × × |
×××○○○○○○○○○○承認について |
×○○○○○○○○○○○(○○○年清水町条例第○○号)第○条第○項の規定に基づき、○○○年○月○○日○○第○○号で申請のあったものを承認する。 |
(6) 申請
ア
○第○○○号× |
○年○月○日× |
×○○知事×○○○○様 |
清水町長×氏 名 × × |
×××○○○年度○○補助金の交付について(申請) |
×○○○年度○○事業について、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 |
記 |
○○○○○○ |
イ
| | | | | | ○第○○○号× | |
| | | | | ○年○月○日× | |
×○○知事×○○○○様 | | | | | |
| | | | 清水町長×氏 名 × × | |
×××○○○年度○○事業の起債許可について(申請) | | | |
×○○○年度一般補助事業(災害復旧事業及び高校施設整備事業)に充当するための起債について町議会の議決を経ましたので、次のとおり許可くださるよう関係書類を添えて申請します。 | |
区分 | 事業名 | 許可予定決定通知額 | 議決額 | 許可申請額 | 資金区分 | 摘要 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(7) 依命通知
| ○第○○○号× |
○年○月○日× |
×○○○○×○○○○様 |
| 清水町長×氏 名 × × |
×××件名○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×× |
| ○○○○について(依命通知) |
×本文○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○するよう、命により通知する |
×なお、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
記 |
1×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○○○○。 |
(8) 通知、照会、回答、報告書
| ○第○○○号× |
○年○月○日× |
×○○○知事×○○○○様 |
| 清水町長×氏 名 × × |
×××件名○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×× |
| ○○○○について(通知) |
×本文○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
×なお、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
記 |
1×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
×(1)×○○○○○○○○○○○○。 |
××ア×○○○○○○○○○○○○○○○。 |
×××(ア)×○○○○○○○○○○○○。 |
××××a×○○○○○○○○○○○○○。 |
題名(件名)の末尾には、必ず「通知」、「照会」など括弧書きし、その文書の性質を明らかにすること。
(9) 裁決書
| ○○○第○○号× |
裁 決 書 |
| 審査請求人 |
住所○○○○○○○○○×× |
氏名○○○○○○○○○× |
年 齢 ○○ 歳× |
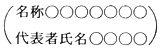
|
×××主文 | |
×審査請求人の審査請求は、棄却する。(却下する。認容し、○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○○○○を取り消す。) |
×××請求の趣旨 | |
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
×××理由 | |
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
×よって、○○○○法第○○条第○○項の規定に基づき、主文のとおり裁決する。 |
×○○○年○○月○○日 | |
清水町長×氏 名印× |
(10) 諮問
| ○○○第○○号× |
| ○年○月○○日× |
×○○○審議会会長 | |
○ ○ ○ ○ 様 | |
| 清水町長×氏 名印× |
×××○○○○について(諮問) |
×○○○○○○○のため(○○○○○することにつき、)(○○○○○について次のとおり)貴会の意見を求めます。 |
(11) 願及び届
○ ○ 届 |
○年○月○○日× |
×清水町長×○○○○ 様 |
| ○○課○○係 |
| 職名×○○○○印× |
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
記 |
(12) 表彰状
(13) 感謝状
(14) 賞状
注 賞状は、内容等により横書きとしてもよい。
4 文書のとじ方
文書は、左とじとする。
5 用紙
用紙は、原則として日本標準規格によるA4判を用い、A4判により難いものについてはA5判又はA6判を縦長にして用いる。
第10 条例・規則の書式
1 公布文
公布文は、法令を公布する旨の公布者の意思を表明する文書で、町長が署名する。
(1) 公布文の初字は第2字目からとし、2行以上にわたる場合は、2行目からの各行は、第1字目からとする。
(2) 公布年月日の初字は、第3字目からとする。
(3) 町長名(署名)の最終字は、末尾から2字目とし、職名と氏名との間を1字空ける。
2 番号
(1) 条例・規則には、公布の際、条例又は規則番号を付け、番号は、暦年ごとに一連番号で付ける。
(2) 番号の初字は、第1字目からとする。
3 題名
(1) 題名は、その内容を簡潔に表現するものとする。
(2) 新しく制定する条例・規則には、「何々条例(規則)」「何々に関する条例(規則)」というような題名を付け、既存の条例・規則の一部を改正する条例・規則には、「何々条例(規則)の一部を改正する条例(規則)」、「何々に関する条例(規則)の一部を改正する条例(規則)」というような題名を付けるものとする。
(3) 題名は、第4字目から書き出し、2行以上にわたるときも、また4字目から並べて書くものとする。
(4) 題名を改正する場合は、題名を改正する旨の柱書の次に本来題名を置くべき位置に改正される題名を書くものとする。
4 目次
(1) 条例・規則の本則の内容が章、節等に分かれている場合は、目次を置くものとする。
(2) 目次の初字の位置は、第1字目とする。目次には、編、章、節等ごとに、その編、章、節等のそれぞれに属する条文の範囲を括弧で、附則は、単に附則と示すものとする。
(3) 括弧書きの条名が3条以上にわたっているときは、例えば「(第1条―第4条)」と「―」でつなぎ、2条の場合は、「(第○条・第○条)」と「・」でつなぐものとする。
5 本則
(1) 本則が条で成り立っている場合の配字は、第1字目から「第何条 何々」とする。
(2) 条中の項は、第2項から項の上に算用数字で2、3…と順を追って表示し、算用数字の位置は、その項の第1行第1字目とし、本文は、第1行目は第3字目から、第2行目以下は第2字目から書くものとする。
(3) 内容が簡単なものは、項のみとすることができる。この場合には、項が2項以上あるときは第1項から1、2、3…と表示し、項が1項のみのときは、項番号を付さない。
(4) 条文は項の中において事物の名称等を列記する場合には、号を用いる。号は、(1)、(2)、(3)、をもって表し、その配字は、第2字目からとする。号の中に更に列記の必要があるときは、「ア、イ、ウ」を用い、その配字は、第3字目からとする。「ア、イ、ウ」の中を更に細分する必要があるときは、(ア)、(イ)、(ウ)とする。
(5) 見出しは、1条ごとに付するものとするが、連続する2以上の条文が同じ内容に属する事項を規定している場合には、前の条文にまとめて見出しを付けることができる。見出しは、条文の左上に括弧書きとし、括弧の左が第2字目の右の部になるようにするものとする。
(6) 本則中に、編、章、節等の区分がある場合の題名、章名、節名の配字は、編名の初字は第3字目、章名の初字は第4字目、節名の初字は第5字目、とする。
(7) 条例・規則中に他の法令名を引用する場合には、その法令の題名又は件名を掲げ、その右に公布年及び法令番号を括弧書きにするものとする。ただし、一の法令中に同一の法令名を2回以上引用する場合には、最初の引用の時にだけ公布年及び法令番号を括弧書きにする。
6 附則
(1) 附則は、項に分けて規定するものとする。ただし、内容が複雑である場合には、条を置くことができ、そのときは附則だけで新たな条の番号を付けるものとする。
(2) 附則が項で成り立っている場合には、附則が一つの項のみのときは項番号を付けず、二つ以上の項で成り立っているときは、第1項から1、2等の項番号を付け、附則各項には、条の場合に準じ、見出しを付けるものとする。
(3) 附則に規定すべき事項は、通常は、法令の施行期日に関する事項、既存の法令の改廃に関する事項、経過的措置に関する事項とし、そのほかに、限時法である場合には有効期限を定め、又は本則に書くことを適当としない臨時的な規定を設けるものとする。
(4) 附則における規定は、ア その条例・規則の施行期日に関する規定 イ 既存の条例・規則の廃止に関する規定 ウ その条例・規則の制定に伴う各規定の適用関係に関する規定 エ ウ以外の他の経過措置に関する規定 オ 既存の条例・規則の改正に関する規定 カ オの改正規定に伴う経過措置に関する規定を設けることを通例とする。
(5) 附則の「附」の字は第4字目、「則」の字は第6字目とする。
(6) 文章は第2字目から書くが、項を設けたときは、5の(2)の例によるものとする。
7 書式は、次の表のとおりとする。
(1) 新規制定の条例(規則)(公布文を含む。)
清水町条例第○○号 | | |
×○○○○○○○○条例(規則)をここに公布する。 | |
××○○○年○○月○○日 | | |
| | 清水町長×(氏 名)× |
×××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
×××○○○条例(規則) | | |
目次 | | |
×第1編×○○○○○ | | |
××第1章×○○○○○ | | |
×××第1節×○○○○○ | | |
××××第1款×○○○○○(第1条―第○条) | |
××××第2款×○○○○○(第○条・第○条) | |
×××第2節×○○○○○(第○条―第○条) | |
××第2章×○○○○○(第○条―第○条) | |
××第3章 ○○○○○ | | |
×××第1節 ○○○○○(第○条―第○条) | |
| (中略) | | |
×附則 | | |
××第1編×○○○○○ | | |
×××第1章×○○○○○ | | |
××××第1節×○○○○○ | | |
×××××第1款×○○○○○ | | |
×(○○) | | |
第1条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。ただし、○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○○○。 |
×(○○) | | |
第2条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 | |
×(○○) | | |
第3条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 | |
×(1)×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××○○○○○○○○○○○。 |
×(2)×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 | |
| (中略) | | |
×××附×則 | | |
1×この条例(規則)は、公布の日から施行する。 | |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○。 |
別表(第○条関係) | | |
| ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○○ | |
| | |
(2) 一部改正の条例(規則)
×××○○○○条例(規則)の一部を改正する条例(規則) |
×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第〇号)の一部を次のように改正する。 |
×第○条中「○○○」を「○○○」に改める。 (条文中一部の改正) |
×第○条第○項中「○○」の次に「○○」を加える。(条文中一部の規定の追加) |
×第○条第1項中ただし書きを削り、同条第3項中に次のただし書きを加える。 |
××ただし、○○○○○○○○○○○。 (ただし書きの削除と追加) |
×第○条の見出しを「(○○○)」に改める。 (見出しの改正) |
×第○条の次に次の1条を加える。 |
第○条の2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (1条追加) |
×第○条第○項第○号を削る (末尾の号の削除) |
×第○条第○項に後段として次のように加える。 |
××この場合において、○○○○○○○○○○。 (後段の追加) |
×第○条の見出し中「○○」を「○○」に改める。 (見出し中の改正) |
×第○条を次のように改める。 |
第○条×削除 (その条の全文の削除) |
×第○条を次のように改める。 |
第○条×○○○○○○○○○○○○○○○○。 (条文全文の改正) |
×別表中「○○○」を「○○○○」に改める。 (別表中の改正) |
×××附×則 |
1×この条例(規則)は、○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
(3) 2以上の条例(規則)の同時改正
×××○○○○条例(規則)等の一部を改正する条例(規則) |
第1条×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)の一部を次のよ×うに改正する。 |
××第○条中「○○」を「○○」に改め、「○○○」を削る。 |
××第○条を次のように改める。 |
×第○条×○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
第2条×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)の一部を次のよ×うに改正する。 |
××第○条中第○号を削り、第○号を第○号とし、第○号から第○号までを○号ずつ繰×り上げる。 |
第3条×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)の一部を次のよ×うに改正する。 |
××第○条第○項中「○○」の次に「○○」を加える。 |
×××附×則 |
1×この条例(規則)は、○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
(4) 全部改正の条例(規則)
×××○○○○条例(規則) |
×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)の全部を改正する。 |
×(○○) | |
第1条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
×(○○) | |
第2条×○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○○○○○○○○。 |
(中略) | |
×××附×則 | |
1×この条例(規則)は、○○○年○○月○○日から施行する。 |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
(備考)附則には既存の条例を廃止する旨の規定を置かない。
(5) 一つの条例(規則)の廃止
×××○○○○条例(規則)を廃止する条例(規則) |
×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)は、廃止する。 |
×××附×則 |
×この条例(規則)は、○○○年○○月○○日から施行する。 |
(6) 2以上の条例(規則)の廃止
×××○○○○条例(規則)等を廃止する条例(規則) |
第1条×○○○○に関する条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)は、廃×止する。 |
第2条×○○○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)は、廃止す ×る。 |
×××附×則 |
1×○○○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○。 |
第11 訓令の書式
1 制定(全文改正)
清水町訓令第○○号 | |
| 庁中一般× |
支 所× |
その他の機関× |
(あて名) |
×公印規程を次のように定める。 | |
××○○○年○○月○○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
×××公印規程 | |
×(趣旨) | |
第1条×この訓令は、公印の種類、保管及び使用について、必要な事項を定めるものと×する。 |
(中略) | |
×××附×則 | |
×(施行期日) | |
1×この訓令は、公布の日から施行する。 | |
×(旧訓令の廃止) | |
2×公印規程(○○○年清水町訓令第○○号。以下「旧訓令」という。)は、廃止す ×る。 |
(中略) | |
4×この訓令の施行前に旧訓令によって告示された公印は、この訓令によって告示され×たものとみなす。 |
2 一部改正
清水町訓令第○○号 | |
| 庁中一般× |
支 所× |
(あて名) |
×○○○○規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |
××○○○年○○月○○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
×××○○○○規程の一部を改正する訓令 | |
×○○○○規程(○○○年清水町訓令第○号)の一部次のように改正する。 |
×第○条第○項中「○○○」を「○○○」に改め、「○○○」を削る。 |
×第○条及び第○条中「○○」の次に「○○○○○○○」を加える。 | |
×××附×則 | |
×この訓令は、○○年○○月○○日から施行する。 | |
3 廃止
清水町訓令第○○号 | |
| 庁中一般× |
支 所× |
(あて名) |
×○○○○○○○○規程を廃止する訓令を次のように定める。 | |
××○○○年○○月○○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
×××○○○○○○○○規程を廃止する訓令 | |
×○○○○○○○○規程(○○○年清水町訓令第○号)は、廃止する。 |
×××附×則 | |
×この訓令は、○○○年○○月○○日から施行する。 | |
第12 告示その他公告の書式
1 告示
(1) 制定
清水町告示第○○号 | |
×○○条例(規則)(○○○年清水町条例(規則)第○号)第○条の規定に基づき、○○から届出があった。(次のように告示する。)(次のとおり指定する。)(次のとおり公表する。)(○○は、次のとおりとする。)(次のように定め、○○○年○月○日から適用する。)(この処分は○○○年○月○日から○○とする。) |
××○○○年○月○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
1×○○○○○○○○○○○○○。 | |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 | |
(2) 一部改正
清水町告示第○○号 | |
×○○○年清水町告示第○○号(○○○○○○○○)の一部を次のように改正し、○○○年○○月○○日から施行(適用)する。 |
××○○○年○月○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
×「○○○」を「○○○○」に改める。 | |
(3) 廃止
清水町告示第○○号 | |
×○○○年清水町告示第○○号(○○○○○)は、廃止する。 | |
××○○○年○○月○○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
2 公告
×○○○○○条例(○○○年清水町条例第○○号)第○条の規定に基づき、○○○年○月○日付けで清水町○○○委員会委員を次のとおり任命した。 |
××○○○年○○月○○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
○○○○××○○○○ | |
○○○○××○○○○ | |
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○した(する。である。があった。)。 |
××○○○年○○月○○日 | |
清水町長×○○○○× |
| (氏名) |
1×○○○○○○○○○○○。 | |
2×○○○○○○○○○○○○○○○○。 | |
参考 条例・規則の改正の書式例
1 題名の改正
(備考) 新たな題名は4字目から書き出すこと。
2 条文全部の改正
(1) 1条全文を改正する例
×第○条を次のように改める。 |
×(○○) |
第○条×○○○○○○○○○○○○。 |
(2) 項の全文を改正する例
ア
×第○条第2項を次のように改める。 |
2×○○○○○○○○○○○○。 |
イ
×第○条第1項から第3項までを次のように改める。 |
第○条×○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○。 |
3×○○○○○○○○○○○○。 |
(3) 号の全文を改正する例
×第○条(第○項)第3号を次のように改める。 |
×(3)×○○○○○○○○。 |
(4) ただし書の全文を改正する例
×第○条(第○項)(第○号)ただし書を次のように改める。 |
××ただし、○○○○○○○○。 |
(5) 別表を改正する例
×別表(第○)を次のように改める。 |
別表(第○) | |
× | ○ ○ | ○ ○ | |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | |
| ○○○ | ○○○○○○○○ | |
| | | |
3 条文の一部の改正
(1) 条文中ある字句を改正する例
ア 一つの条文中において一箇所のみ改める例
×第○条中「○○」を「○○」に改める。 |
×第○条第○項(第○条第○号)中「○○」を「○○」に改める。 |
×第○条第○項第○号中「○○」を「○○」に改める。 |
×第○条(第○項、第○号)ただし書(本文)中「○○」を「○○」に改める。 |
×第○条(第○項)各号列記以外の部分中「○○」を「○○」に改める。 |
(注)改めようとする字句の位置に応じ、当該条文の最小単位の区分まで引用する。
イ 同一の条文中数項にわたって改正する例
×第○条第1項中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改め、同条第3項中「○○○」を「○○」に改める。 |
(備考)同一条文の同一項内に2箇所以上の改正を必要とする場合は、一つ一つ「改める」の文字を用いることなく、末尾にのみ記載する。また項が2項以上にまたがっているときは、項ごとに「改め、」とするのが用例である。
ウ 数条にわたって同一字句を改正する例
×第○条、第○条第○項、第○条及び第○条中「○○」を「○○」に改める。 |
×第○条から第○条までの規定中「○○」を「○○」に改める。 |
×本則及び附則中「○○」を「○○」に改める。 |
(注) 途中の条文中に他の字句について改める必要があるときは、その条文の前でいったん切り、当該条文についての改正を行う。
(2) ある字句を追加する例
×第○条第○項中「○○」の次に「○○○○○○」を加える。 |
(3) ある字句を削る例
(4) ある字句を改め、追加し、及び削る例
×第○条中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改め、「○○」の次に「○○○」を加え、「○○」を削る。 |
×第○条第1項中、「○○」を「○○」に改め、同条第3項中「○○」の次に「○○○」を加え、同項第○号中「○○」を削る。 |
(5) 表又は別記様式の一部改正例
×別表(第○条の表)○○の項中「○○」を「○○」に改め、○○の項を次のように改める |
× | ○ ○ | ○○○○○○○○○○○ | |
| | | |
4 条文の追加
(1) 章(節)を追加(条文を含めて)する例
×第1章の次に次の1章を加える。 |
×××第1章の2×○○○○ |
第○条の2×○○○○○○○○。 |
第○条の3×○○○○○○○○。 |
2×○○○○○○○○○○○。 |
(2) 条を追加する例
ア 枝番号を用いる例(条の繰下げを行わない場合)
×第4条の次に次の1条を加える。 |
第4条の2×○○○○○○○○。 |
イ 繰り下げる例
×第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。 |
第6条×○○○○○○○○。 | (注1) |
×第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。 |
第5条×○○○○○○○○。 | (注2) |
(注1) 繰り下げる条が3以下の場合
(注2) 繰り下げる条が4以上の場合
ウ 末尾に追加する例
×第9条の次に次の1条を加える。 |
第10条×○○○○○○○○。 |
×第○章(第○節)中第○条の次に次の1条を加える。 |
第○条の2×○○○○○○○○。 |
(3) 項を追加する例
ア 第1項の前に追加する例
×第○条中第5項を第6項とし、第1項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、同条に第1項として次のように加える。 |
第○条×○○○○○○。 |
イ 項と項との間に項を追加する例
×第○条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 |
2×○○○○○○○○。 | (注1) |
×第○条中第5項を第7項とし、第2項から第4項までを2項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の2項を加える。 |
2×○○○○○○○○○○○。 | |
3×○○○○○○○○。 | (注2) |
(注1) 繰り下げる項が3以下の場合
(注2) 繰り下げる項が4以上の場合
ウ 末項の次に追加する例
×第○条に次の1項を加える。 |
4×○○○○○○○○。 |
(4) 号を追加する例
ア 第1号の前に追加する例
×第○条(第○項)中第5号を第7号とし、第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第3項の前に次の2号を加える。 |
×(1)×○○○○○○。 |
×(2)×○○○○○○○○○。 |
イ 号と号との間に号を追加する例
×第○条(第○項)中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 |
×(3)×○○○○○○○。 | (注1) |
×第○条(第○項)中第10号を第11号とし、第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の1号を加える。 |
×(6)×○○○○○○○○○○○。 | (注2) |
×第○条第3号の次に次の1号を加える。 | |
×(3)の2×○○○○○○○○。 | (注3) |
(注1) 繰り下げる号が3以下の場合
(注2) 繰り下げる号が4以上の場合
(注3) 繰り下げを行わない場合
ウ 末号の次に追加する例
×第○条(第○項)に次の2号を加える。 |
×(3)×○○○○○○。 |
×(4)×○○○○○○○○○。 |
(5) ある項にただし書又は後段を追加する例
×第○条(第○項)に次のただし書を加える。 |
××ただし、○○○○○○○○。 |
×第○条第○項に後段として次のように加える。 |
××○○○○○○、○○○○○○、また同様とする。 |
(6) 表又は表の項を追加する例
×次の別表を加える。 | |
× | ○ ○ | ○ ○ | |
| ○○○○ | ○○○○○○ | |
| ○○○○ | ○○○○○○ | |
×別表(第○条の表)○○の項の次に次のように加える。 |
× | ○○○○ | ○○○○○○ | |
| | | |
(7) 見出しを付ける例
5 条文の削除
(1) 条を削除する例
ア 条と条との中間にある全文を削除するが、条そのものは存置する例
×第○条を次のように改める。 |
第○条×削除 |
×第○条から第○条までを次のように改める。 |
第○条から第○条まで×削除 |
×第8条及び第9条を次のように改める。 |
第8条×削除 |
第9条×削除 |
イ 条文をすべて削除し、かつ、条そのものも削除する例
×第○条を削る。 | (注1) |
|
×第6条及び第7条を削り、第8条を第6条とし、第9条を第7条とし、第10条を第8条とする。 |
| (注2) |
×第6条を削り、第7条を第6条とし、第8条から第10条までを1条ずつ繰り上げる。 |
| (注3) |
(注1) 繰上げが不用な場合
(注2) 繰り上げる条が3以下の場合
(注3) 繰り上げる条が4以上の場合
(2) 項を削除する例
×第○条中第○項及び第○項を削る。 | (注1) |
×第○条中第4項及び第5項を削り、第6項を第4項とし、第7項を第5項とし、第8項を第6項とする。 |
| (注2) |
×第○条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項から第8項までを1項ずつ繰り上げる。 |
| (注3) |
(注1) 繰上げが不用な場合
(注2) 繰り上げる条が3以下の場合
(注3) 繰り上げる条が4以上の場合
(3) 号を削除する例
×第○条(第○項)中第○号を削る。 | (注1) |
×第○条(第○項)第3号及び第4号を次のように改める。 | |
×(3)及び(4)×削除 | (注2) |
(注1) 末尾の号を削る場合
(注2) 繰り上げを行わない場合。ただし、繰り上げを行う場合は、「項を削除する例」を参照のこと。
(4) ただし書又は後段を削除する例
×第○条(第○項第○号)ただし書(後段)を削る。 |
×第○条(第○項)ただし書(後段)及び各号を削る。 |
(5) 表(様式)を削除する例
附 則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の清水町公用文作成に関する規程の規定に基づいて作成されている様式又は用紙がある場合においては、この訓令による改正後の清水町公用文作成に関する規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成6年9月14日訓令第17号)
この訓令は、平成6年9月14日から施行する。
附 則(平成20年3月13日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日訓令第7号)
この訓令は、平成22年11月30日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
 又は2分の1
又は2分の1
 」
」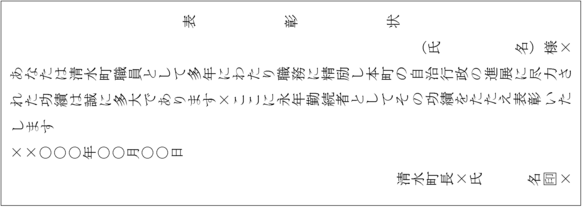
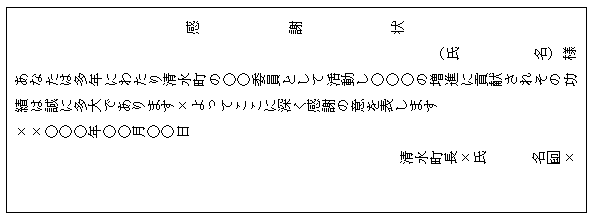
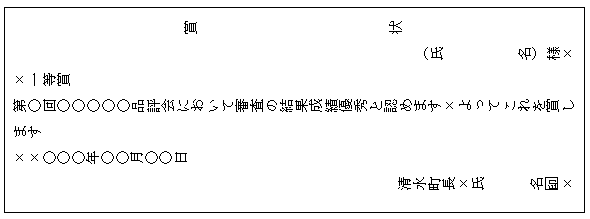










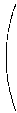
























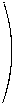



 ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×